

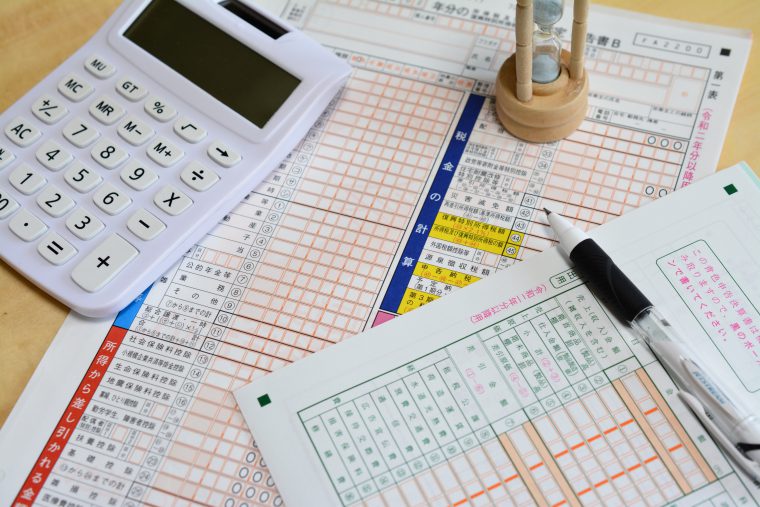
みなさんこんにちは!税理士法人リライトの相続業務担当スタッフです!
所得税の確定申告の際には、「医療費控除」「寄付金控除」「住宅ローン控除」といった様々な控除が存在しますが、もちろん相続税にも様々な控除が存在します。また、相続税の計算においては、相続が発生した日(=被相続人が亡くなった日)の状況を基に判断されますので、今該当したとしても、実際の相続発生時に該当するとは限りません。
今回は、そんな相続税に関する様々な控除についてご紹介します!
相続税の計算でまず出てくるのが、「基礎控除」です。相続税における基礎控除は、法定相続人の数に応じて変動します。まず、すべての相続に共通して存在する基礎控除額の3,000万円があり、法定相続人1名につき600万円の控除額があります。例えば、相続人が配偶者と子供1人であった場合は、3,000万円+600万円×2名=4,200万円となります。
従って、相続財産の合計額から債務や葬儀費用等の価額を引いた価額(純資産価額)が基礎控除額を超えなければ、相続税は発生せず、申告も必要が無いということになります。
相続開始3年以内(2027年1月1日以降随時7年以内に拡大)に被相続人が相続人へ暦年贈与をしていた場合、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。この加算した贈与財産について贈与税を支払っていた場合は、その贈与税額に相当する金額を相続税額から控除することができます。ただし、相続税額よりも贈与税額が高く、控除しきれない分がある場合は、暦年課税分については還付はありません。
なお、贈与税額控除については自動で反映されるものではなく、申告をしないと税額には反映されませんので、きちんと計算をして申告をする必要があります。
相続時精算課税制度を適用して贈与をした場合は、その贈与した時期に関わらずその財産を相続財産に計上しなければなりません。この贈与時に贈与税を支払っていた場合は、暦年贈与分と同じように、その贈与税額に相当する金額を相続税額から控除することができます。また、相続税額よりも贈与税額が高く、控除しきれない分がある場合は、暦年贈与分とは異なり還付を受けることができます。還付を受けるには申告をすることが必要ですので、贈与税申告書等の資料は必ず大切に保管し、相続税申告時にすぐに確認できるようにすることが大切です。
被相続人の配偶者が財産を相続する場合、その配偶者が取得する相続財産の評価額が1億6,000万円、もしくは法定相続分のいずれか多い額の範囲までは相続税が非課税となります。例えば、相続人が配偶者と子供1人の計2名で相続財産が10億円ある場合は、配偶者が相続する財産のうち5億円までは非課税となります。また、仮に相続人が配偶者だけの場合は、配偶者の法定相続分=相続財産の総額となりますので、相続財産すべてが非課税となります。
なお、配偶者の税額軽減は、申告をしないと適用できないため、配偶者の税額軽減を適用することで税額が0円になったとしても必ず申告が必要になります。
相続人が未成年者であった場合は、その未成年者の年齢に応じた額が、その未成年者が支払うべき相続税額から控除されます。控除額は、(18歳-未成年者の相続時の年齢)×10万円になります。また、未成年者控除額がその未成年者の相続税額よりも多く控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。なお、未成年者控除には申告要件がありませんので、未成年者控除を適用することで相続税額が0円になる場合は、相続税申告の必要はありません。ちなみに、この未成年者控除は胎児であっても該当するため、相続発生時点で相続人に胎児がいた場合は、未成年者控除が適用できます。
ただし、未成年者控除を適用するには、該当する未成年者が相続財産を取得する必要がありますので、注意が必要です。また、その未成年者が過去の相続税申告で既に未成年者控除を受けている場合は、今回の未成年者控除額と、過去に適用した未成年者控除額(18歳を限度とする)のうち控除しきらなかった残額のいずれか少ない額が、控除できる額となります。従って、過去の相続税申告で未成年者控除を全額適用していた場合は、以後の相続税申告で未成年者控除を適用することはできません。
相続人が85歳未満の一定のレベルの障害者である場合は、その障害者の年齢に応じた額が、その障害者が支払うべき相続税額から控除されます。また、該当要件や控除額は一般障害者と特別障害者で異なります。
〇一般障害者 〇特別障害者
・身体障害者3~6級 ・身体障害者1~2級
・精神障害者保健福祉手帳2~3級 ・精神障害者保健福祉手帳1級
・療育手帳3~4度(B・C) ・療育手帳1~2度(A)
・戦傷者手帳第4~第6項症該当 ・戦傷者手帳第1~第3項症該当
・原爆症認定者
・成年被後見人
・6か月以上寝たきりの要介護者
控除額…(85歳-相続時の年齢)×10万円 控除額…(85歳-相続時の年齢)×20万円
なお、未成年者控除と同様に、障害者控除額がその障害者の相続税額よりも多く控除しきれない場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、障害者控除を適用することで相続税額が0円となった場合は、相続税申告の必要はありません。
ただし、障害者控除を適用するには、該当する障害者が相続財産を取得する必要があります。また、その障害者が過去の相続税申告で既に障害者控除を受けている場合は、今回の障害者控除額と、過去に適用した障害者控除額のうち控除しきらなかった残額のいずれか少ない額が、控除できる額となります。従って、過去の相続税申告で障害者控除を全額適用していた場合は、以後の相続税申告で障害者控除を適用することはできません。
被相続人が、相続発生前10年以内に自身が相続人となって相続税を支払っていた場合、その相続税額と申告年に応じた額を今回の相続税額から控除することができます。控除額の計算についてはかなり複雑になっていますので、基本的には専門の税理士等に相談することをおすすめします。
外国にある相続財産を相続した場合、その相続財産がある外国の相続税を支払う可能性があります。この場合、同じ財産に日本でも外国でも税金が課せられてしまう形になりますので、外国で支払った税額分については、日本の税額から控除することができます。控除できる税額は、外国で実際に支払った日本の相続税に相当する税額又は、日本で実際に発生した相続税額×国外財産の価額÷相続財産の総額の、いずれか低い金額となります。

このように、相続税においても様々な控除が存在します。それぞれ要件が複雑であったり控除額の計算が煩雑なものが多いので、特例や控除の適用忘れや間違った申告にならないように、申告の際は必ず税務署や専門の税理士等に相談しましょう!
電話でのお問い合わせ
(土日祝除く 10:00~17:00 まで)
03-6555-4383